株価
三菱自動車とは
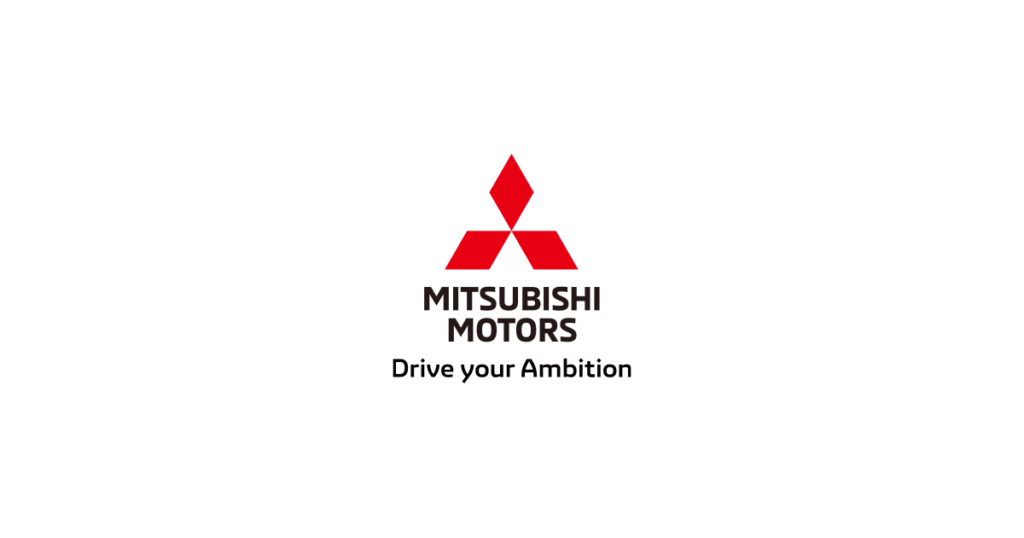
三菱自動車工業は、日本の大手自動車メーカーの中でも「SUV・4WD・ピックアップトラック」に圧倒的な強みを持つ企業として知られている。1970年に三菱重工から独立して以降、独自の四輪駆動技術や耐久性の高い車づくりで国内外の信頼を築いてきた。東京都港区芝浦に本社を構え、現在は日産・ルノー連合とアライアンスを組み、技術開発や生産効率の向上を図りながらグローバルに事業展開している。
三菱自動車の最大の特徴は、なんといっても“悪路走破性”“耐久性”に優れた車両づくりだ。名車「パジェロ」で培った本格四輪駆動技術は、今もSUV「パジェロスポーツ」やピックアップトラック「トライトン」に継承されており、砂漠・山岳・東南アジアの過酷な道路環境でも問題なく走れる車として高い評価を受けている。国内では「アウトランダー」「エクリプスクロス」「デリカD:5」などが人気車種として定着しており、“三菱といえば頑丈なSUV”というイメージを確立している。
販売戦略の中心はアジア市場だ。特にタイ・インドネシア・フィリピンなど東南アジアでは圧倒的な存在感を持ち、ピックアップ市場では「トライトン」がトップクラスの人気を誇る。国内市場以上に海外売上比率が高いのが三菱自動車の特徴であり、アジア新興国の成長がそのまま業績に反映されやすい構造になっている。これは他の日本メーカーにはない大きな強みでもある。
さらに、三菱自動車は“電動車の先駆者”でもある。実は世界で最も早く量産EVを発売したメーカーの一つであり、軽EV「i-MiEV」は業界の先駆けとなった。また「アウトランダーPHEV」は世界的な成功を収め、PHEV(プラグインハイブリッド)領域では世界トップレベルの技術を持つ。日産・ルノーとのアライアンスにより、今後はプラットフォーム共有や共同開発が加速し、電動車ラインアップの拡充が期待されている。
一方で、三菱自動車は軽自動車燃費不正問題の影響が長く残り、その後の経営立て直しには時間がかかった過去がある。しかしアライアンス参加後はコスト削減が進み、収益構造は改善傾向。現在ではSUV/トライトンのグローバル需要が成長を支え、アジア市場での競争力も回復してきている。
総合すると、三菱自動車は他の大手自動車メーカーとは異なり、「SUV・ピックアップ・4WD・アジア市場」に強みを集中させた、非常に個性のあるグローバルメーカーである。電動車の技術も持ち、アライアンスの恩恵で開発効率も上がっており、今後の業績成長はアジア市場の需要動向とSUV戦略の成否に大きく左右されると言える。
三菱自動車 公式サイトはこちら直近の業績・指標
| 年度 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 一株益(円) | 一株配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3 | 2,458,141 | 190,495 | 182,022 | 168,730 | 113.4 | 5 |
| 2024/3 | 2,789,589 | 190,971 | 209,040 | 154,709 | 104.0 | 10 |
| 2025/3 | 2,788,232 | 138,826 | 98,602 | 40,987 | 28.7 | 15 |
| 2026/3(予) | 2,860,000 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 7.5 | 10 |
出典元:四季報オンライン
キャッシュフロー
| 年度 | 営業CF(百万円) | 投資CF(百万円) | 財務CF(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2023/3 | 173,576 | -53,145 | -61,865 |
| 2024/3 | 140,806 | -138,865 | 37,674 |
| 2025/3 | 174,734 | -114,752 | -274,765 |
出典元:四季報オンライン
バリュエーション
| 年度 | 営業利益率 | ROE | ROA | 実績PER(高値平均) | 実績PER(安値平均) | 実績PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3 | 7.7% | 21.0% | 7.6% | ― | ― | ― |
| 2024/3 | 6.8% | 15.3% | 6.3% | ― | ― | ― |
| 2025/3 | 4.9% | 4.3% | 1.8% | 10.8倍 | 6.3倍 | 0.58倍 |
出典元:四季報オンライン
投資判断
三菱自動車工業は、直近3年間の業績推移を見ると、売上はおおむね横ばいで推移しているが、利益面では明らかに減速傾向が見える企業だ。まず営業利益を見ると、2023年は1,904億円、2024年も1,909億円とほぼ横ばいを維持していたが、2025年には1,388億円まで縮小している。経常利益も1,820億円 → 2,090億円 → 986億円と大きく落ち込み、最終利益に至っては1,687億円 → 1,547億円 → 409億円と、3年で約4分の1まで縮小している。ここだけを見ると、事業環境が明らかに厳しくなっていることが分かる。
収益性についてもはっきり弱含んでおり、営業利益率は2023年の7.7%から2024年に6.8%、さらに2025年には4.9%まで低下している。営業利益率が5%を切ると、自動車メーカーとしては「低収益」の部類に入り始めるため、このあたりのトレンドは注意が必要だ。ROEも21.0% → 15.3% → 4.3%と急激に縮小しており、企業が株主資本を有効に使えていない状況が浮き彫りになっている。ROAも7.6%から1.8%まで落ち込んでおり、資産全体の収益効率も大きく低下している。
株価指標を見ると、2025年度の実績PERは高値平均10.8倍、安値平均6.3倍で推移している。PER6倍台はかなり割安な水準ではあるが、それは裏を返せば「市場が成長性をあまり評価していない」という意味でもある。また、PBR0.58倍という数字は、純資産の半額以下で放置されている状態を示しており、投資家の評価は全体的に厳しい。低PBR銘柄は“復活すれば一気に見直される可能性はある”ものの、“復活しなければそのまま放置”されるケースも多く、いわゆるバリュートラップに近い状態にも見える。
総合的に判断すると、三菱自動車は現在「利益縮小・収益性低下・市場評価は割安」という3つが重なっている局面だ。売上は一定水準を維持しているものの、利益が追いついておらず、成長企業というよりは再び立て直しのフェーズに戻っている印象が強い。東南アジアでの競争激化や為替、電動化投資負担など、外部要因も利益を圧迫しやすい状況が続いている。
ただし、PBR0.5倍台というのは市場が極端に悲観している水準であり、何らかのきっかけで利益が底を打って回復傾向に入れば、株価が大きく見直される可能性はある。つまり「リスクは高いが反発余地もそれなりにある銘柄」という位置づけになる。
結論としては、短期的には収益悪化が続いているため積極的に買いに動く局面ではないが、長期で業績回復に賭けたい投資家や、割安水準で拾いたいバリュー志向の投資家にとっては、監視対象に入れておいても良い銘柄と言える。業績の底打ちサインや営業利益率の改善が見え始めたタイミングが、本格的なエントリーポイントになるだろう。
配当目的とかどうなの?
三菱自動車工業を配当目的で考えた場合、結論から言うと「安定高配当株としては向いていないが、低水準での復配・配当継続なら期待できる」というやや中間的な評価になる。予想配当利回りは26.3期・27.3期ともに2.65%と、日経平均採用銘柄の標準的な利回り(2%台前半)よりやや高めではあるが、高配当株と言えるほどの魅力はまだない。
問題は業績の方向性である。直近の純利益を見ると、2023年の1,687億円から2024年は1,547億円、2025年になると409億円と大幅に縮小しており、利益の落ち込みが配当余力にも直接影響してくる。利益が落ちている中で配当を維持するということは、どうしても会社側が慎重な姿勢を取らざるを得ず、今後の増配余地は限定的になる可能性が高い。
三菱自動車の配当方針は「安定配当+業績連動」が基本で、業績が良いときは増配し、業績悪化時は無理をせずに抑えるタイプの企業である。そのため、現在のように収益性が低下している局面では、配当を極端に増やすよりも手元資金を堅実に確保しておく姿勢が優先される。一方で、配当をゼロにしていない点は好感でき、最低限の株主還元は維持する姿勢があるとも言える。
また、PBRが0.58倍と極端に割安水準で放置されているため、長期的に見れば「株価が大きく戻れば利回りも改善する」可能性はある。ただし、これは業績の反転が前提なので、確実性が高いとは言えない。
総合すると、三菱自動車は「高配当を目当てに買う銘柄」ではなく、「今後の業績回復が見えてきた時に、株価上昇とほどほどの利回りを狙うタイプ」の投資対象となる。現在の利回り2.6%前後は“悪くないが決め手には欠ける”水準であり、もし配当で安定的に収益を取りたいのであれば、より高利回りで業績安定の銘柄のほうが適している。三菱自動車を選ぶなら、あくまで“値上がり期待込みの総合リターン狙い”が前提になるだろう。
今後の値動き予想!!(5年間)
三菱自動車の株価は現在376円だが、今後5年間の動きを考えると、業績の回復度合いや東南アジア市場の動向によって株価の振れ幅は比較的大きくなりそうだ。
まず良いケースでは、同社の強みである新型トライトンやSUVの販売が想定以上に伸び、営業利益率が再び6〜7%台まで戻ってくる展開である。この場合、長年割安に放置されているPBR0.5倍台から0.8〜1.0倍程度までの見直しが入る可能性があり、株価は700〜850円前後まで回復してもおかしくない。特にアジア市場の需要が堅調に推移し、アライアンスを通じた小型車やPHEVの刷新が評価につながれば、株価は中期的に大きく戻る余地がある。
一方で中間的なシナリオでは、売上は微増、利益は横ばい〜小幅改善程度にとどまり、事業としては黒字を維持するものの、劇的な改善までは届かないという展開になる。この場合、株価は400〜550円のレンジで上下しながら、割安評価を保ったまま少しずつ見直される形が続く可能性が高い。配当も安定しているが極端に高いわけではないため、爆発的な人気が出るとは言い難く、ゆっくりとした推移になる。
悪いケースでは、東南アジア市場での競争激化や電動化投資の負担増、為替などの外部要因が悪化し、利益が再び縮小してしまう展開だ。営業利益率が4%を割り込み、純利益も低迷するような状況になると、市場からの評価はさらに厳しくなり、PBRは0.5倍を下回ってしまう可能性がある。この場合、株価は250〜330円あたりまで下落するリスクがあり、業績が本格的に悪化すれば200円台前半まで水準訂正される可能性も否定できない。
総じて言えば、三菱自動車の株価は今後の業績回復の度合いに大きく依存しており、同社のアジア戦略が成功するかどうかが非常に重要なポイントとなる。業績が底打ちして回復基調に入るか、それとも再度の減速に入るかで株価の見通しは大きく変わるため、投資する場合は四半期ごとの業績進捗と市場環境を丁寧に見ていく必要があるだろう。
この記事の最終更新日:2025年11月16日
※本記事は最新の株価データに基づいて作成しています。

コメントを残す