株価
ホンダとは
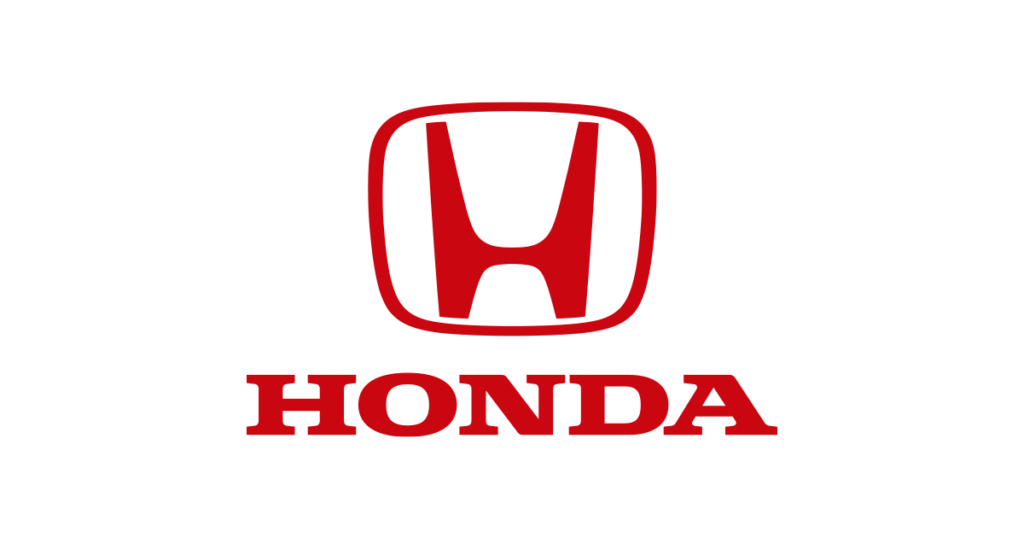
本田技研工業は、日本を代表する総合モビリティメーカーであり、四輪車・二輪車・航空機・パワープロダクツと、事業領域の幅広さでは国内メーカーの中でも際立った存在だ。創業者・本田宗一郎の「人の役に立つ技術をつくる」という哲学を色濃く受け継ぎ、チャレンジ精神と技術革新を武器に世界的企業へ成長してきた。特に二輪車分野では、長年にわたり世界トップクラスのシェアを維持しており、スーパーカブをはじめとした耐久性の高いモデルが世界中の市場で支持されている。四輪車では「N-BOX」や「フィット」「ヴェゼル」「シビック」など、国内外で高い評価を得る人気車種を多数抱え、北米市場ではアコードやCR-Vが強固なブランド力を持つ。
ホンダの特徴は、単なる自動車メーカーにとどまらない事業領域の広さにある。航空機事業では、軽量・低燃費という独自技術を詰め込んだ「HondaJet」が世界的な成功を収め、小型ビジネスジェット市場でもトップクラスの販売実績を誇る。自動車メーカーとして航空機を製造する例は極めて珍しく、ホンダの技術力と挑戦心を象徴する事業といえる。
また、環境技術・電動化にも積極的で、「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、EV、ハイブリッド(e:HEV)、燃料電池(FCV)、水素エネルギーなど多様な技術開発を展開。GM(ゼネラル・モーターズ)との共同開発や、ソニーとの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」による高級EVブランド「AFEELA」など、他社と連携しながら未来のモビリティの形を模索している。
汎用エンジン事業でも発電機、船外機、芝刈り機などを世界市場に供給し、耐久性と燃費性能の高さから産業用・家庭用の双方で高いニーズを持つ。さらにロボティクス領域では「ASIMO」の開発で世界的な注目を集め、現在はロボット技術やAIを用いた新しい移動手段・支援技術の研究も進めている。
総合的に見るとホンダは、「バイク・車・航空機・ロボット・電動化技術」まで扱う、日本でも類を見ない総合モビリティ企業であり、将来の移動手段に対する多角的なビジョンと技術力を持つ会社だといえる。グローバル市場に広がる強固なブランドネットワーク、挑戦的な技術開発、そして幅広い事業領域を背景に、長期的にも成長可能性を秘めた企業として注目される。
ホンダ 公式サイトはこちら直近の業績・指標
| 年度 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 一株益(円) | 一株当り配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3* | 16,907,725 | 780,769 | 879,565 | 651,416 | 128.0 | 40 |
| 2024/3* | 20,428,802 | 1,381,977 | 1,642,384 | 1,107,174 | 225.9 | 68 |
| 2025/3 | 21,688,767 | 1,213,486 | 1,317,640 | 835,837 | 178.9 | 68 |
| 2026/3(予) | 21,500,000 | 800,000 | 810,000 | 485,000 | 123.9 | 70 |
出典元:四季報オンライン
キャッシュフロー
| 年度 | 営業CF(百万円) | 投資CF(百万円) | 財務CF(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2023/3 | 2,129,022 | -678,060 | -1,468,359 |
| 2024/3 | 747,278 | -867,267 | 918,646 |
| 2025/3 | 292,152 | -941,966 | 280,477 |
出典元:四季報オンライン
バリュエーション
| 年度 | 営業利益率 | ROE | ROA | 実績PER(高値平均) | 実績PER(安値平均) | 実績PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3 | 4.6% | 5.8% | 2.6% | ― | ― | ― |
| 2024/3 | 6.7% | 8.7% | 3.7% | ― | ― | ― |
| 2025/3 | 5.5% | 6.7% | 2.7% | 9.7倍 | 6.5倍 | 0.50倍 |
出典元:四季報オンライン
投資判断
ホンダの業績や指標を総合して見ると、「安定感がありながら割安に放置されている、大型優良株」という印象が強い。まず業績面では、売上高そのものが毎期のように伸び続けており、世界的に需要が減る局面でさえ大きく落ちない安定した基盤を持っている。営業利益・経常利益はやや波はあるものの、1兆円規模の利益をコンスタントに出せる体力があり、2024年には営業利益1.38兆円という非常に高い水準を記録している。2025年は一度落ち込むものの、それでも1.2兆円台の利益を確保できている点を考えると、企業としての安定性は相当高い。
収益性の指標を見ても、営業利益率は4.6%、6.7%、5.5%と自動車メーカーとしては十分に高いレベルを維持している。特に2024年の6.7%はトップクラスに近い数字で、その後の5.5%も決して低いわけではない。ROEも5〜8%台で推移しており、資本効率が安定している。ROAも3%前後で、総資産の効率的な運用ができていることが分かる。全体として“強い基礎体力を持つメーカー”という評価が自然だ。
一方、株価指標を見ると、PERは高値平均でも9.7倍、安値平均では6.5倍と低めで、PBRに至っては0.50倍しかない。世界中にファン・販売網があり、航空機やロボティクス事業まで展開している企業としては、この評価は明らかに割安だ。ブランド力やグローバル展開力を考えると、本来であればPBR1倍前後が妥当ラインに思えるが、市場はまだ保守的な評価を続けており、ここに投資妙味が出てくる。
総合すると、ホンダは短期的な利益の上下こそあるが、長期的には安定した収益を維持できる体質を持ち、電動化・航空機・ロボティクスなど将来の成長余地も大きい。それにもかかわらず株価は割安感が残っており、「長期のコツコツ投資」という意味では非常に魅力的な銘柄に入る。極端なバリュー株というよりは「大型のしっかりした企業が安く買える」というイメージに近い。
短期の値動きは為替や世界景気の影響を受けやすいが、じっくり持つには十分すぎる強さがある会社で、長期保有前提なら非常に狙いやすい銘柄だと言える。
配当目的とかどうなの?
ホンダを配当目的で考える場合、現在の水準はかなり魅力的に映る。予想配当利回りは26.3期・27.3期ともに4.49%と、国内大手メーカーの中でも高めの水準に位置しており、安定性の高い大型株としては十分に期待できる利回りだ。自動車株は景気や為替の影響を受けやすい一方で、ホンダは世界中に強固な販売網を持ち、二輪車では圧倒的なトップシェアがあるため、利益の上下があっても長期的には安定してキャッシュを生み続ける体質を持っている。
また、ホンダは配当政策にも一定の規律があり、業績が良いときは増配や特別配当をしっかり出す会社だ。2024年に営業利益が大きく伸びたときも増配を実施しており、株主還元に対して消極的なタイプではない。今期は利益がやや落ち込む見通しだが、それでも4%台後半の利回りを維持する配当を出してくるあたり、財務の強さとスタンスの堅実さが伺える。
さらに魅力的なのは、現状の株価がPBR0.50倍という“かなりの割安圏”にあることだ。純資産から見ても株価が低く評価されている状態で、こうした大手企業の割安局面で高利回りが取れるのは、長期の配当投資家にとっては理想的な環境と言える。PBRが1倍近くまで水準訂正される可能性も残っており、配当だけでなく株価の見直し余地まで含めて期待できる。
総合的に見ると、ホンダは「高利回り × 割安 × 安定した収益基盤」を備えており、配当目的の銘柄として十分に選択肢に入る。もちろん短期の利益は為替や電動化投資などで揺れる可能性があるが、長期目線で安心して持てる大型株としては非常に優秀な部類に入る。4%台後半という利回りがこの規模の企業で得られるのは、今の株価環境がつくる“お得なタイミング”とも言えるだろう。
今後の値動き予想!!(5年間)
ホンダの現在値は1,556.5円だが、今後5年間の株価はグローバル販売の推移やEV戦略の進捗、為替や世界景気の影響を大きく受けることになる。二輪車は世界的に底堅く、四輪は北米市場の強さが続いているものの、電動化の投資負担や欧州規制など不確実性もあるため、シナリオ別に大きく振れる可能性がある。
まず良いケースでは、北米でCR-Vやアコード、シビック系の販売が好調を維持し、新型EV「AFEELA」やe:HEVの浸透が進むシナリオだ。利益率が再び6〜7%台へ戻り、営業利益1.4〜1.6兆円の水準を安定的に確保できれば、市場の割安評価も解消され、PBRが1倍近くまで水準訂正される可能性もある。その場合、株価は2,300〜2,800円程度まで上昇し、長期で見れば3,000円台に届く局面もあり得る。電動化が軌道に乗り、航空機(HondaJet)やロボティクス事業が話題を集めると、上振れ余地はさらに広がる。
中間のケースでは、四輪・二輪ともに堅調だが大きな成長はせず、営業利益1兆円前後を維持する展開だ。EVシフトは進むが利益は薄く、為替や景気の上下が軽く影響する状態で、株価は一定の範囲で安定しやすい。この場合、PBR0.5〜0.7倍のまま推移し、株価は1,450〜1,900円のレンジで動く可能性が高い。時折ニュースで2,000円台にタッチする場面があるものの、明確なブレイクまでは時間がかかるというイメージだ。
悪いケースでは、電動化投資の負担が重い上に、世界景気後退や円高、北米の販売不振が重なるシナリオだ。営業利益率が4%前後に落ち込み、利益が大幅に縮小すると、PBR0.4倍近くまで評価が下がる可能性もある。この場合、株価は1,150〜1,350円程度まで下落するリスクがあり、最悪の局面では1,000円割れも視野に入る。自動車大手は外部環境の影響を受けやすいため、安定的に伸びる未来が保証されているわけではない。
総合すると、ホンダは世界的なブランド力や二輪の強さがあり、大きく崩れにくい一方で、電動化の競争が激しいため上昇の鍵は“EV戦略が軌道に乗るかどうか”にかかってくる。現状の割安さを考えると、長期保有でコツコツ積み上げるタイプの投資とは相性が良い銘柄だといえる。
この記事の最終更新日:2025年11月16日
※本記事は最新の株価データに基づいて作成しています。

コメントを残す