株価
富士通とは
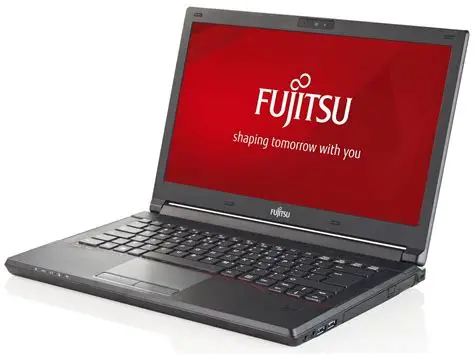
富士通株式会社は、日本を代表する総合ICT(Information & Communication Technology)企業の一つであり、企業や官公庁向けのITインフラ、ソフトウェア、クラウドサービス、ネットワークシステムなど幅広いソリューションを提供している。1935年に古河電気工業とシーメンスの合弁会社として設立され、長年にわたり日本のコンピュータ産業を牽引してきた老舗メーカーである。メインフレームやサーバーに代表されるハードウェア事業に加えて、近年はクラウド移行支援、AI・データ活用、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連サービスなど、ソフトウェア・サービス領域に経営資源を集中している。
同社は世界100カ国以上で事業を展開しており、特に公共・金融・製造・流通など大規模顧客向けのシステム開発や運用支援に強みを持つ。自治体向け基幹システム、医療機関向け電子カルテ、金融機関向けの勘定系システム、企業向けネットワーク基盤など、日本の社会基盤を支えるミッションクリティカルなシステムを多数手掛けている。
また、半導体部門はかつて世界的な規模を誇ったが、現在はロジックLSI事業をスピンアウトし、富士通グループとしてはITサービスに特化する方針を明確にしている。スーパーコンピュータの開発においても高い評価を得ており、理化学研究所と共同開発した「富岳」は世界ランキングで上位を獲得した実績を持つ。AI技術では「Fujitsu Kozuchi(コズチ)」と呼ばれるAIプラットフォームを展開し、製造現場の異常検知、物流最適化、企業のデータ分析支援など多分野で利活用が進んでいる。
環境・社会問題にも積極的に取り組んでおり、カーボンニュートラルや省エネ化を推進するグリーンIT、データセンターの脱炭素化、循環型社会の実現に向けた取り組みを強化している。最近では量子コンピューティング、通信技術、サイバーセキュリティ分野での研究開発も加速しており、国際的にも技術力の高さが注目されている。
富士通は「ITサービス企業への完全転換」を進めており、事業構造改革の中で海外拠点の再編や既存ハードウェアの縮小なども行いながら、高収益なサービスビジネスモデルの構築を目指している。長期的には社会インフラを支えるデジタル基盤企業としての位置づけを確立することを戦略として掲げている。
富士通 公式サイトはこちら直近の業績・指標
| 年度 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 一株益(円) | 一株配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◇23.3* | 3,713,767 | 335,614 | 371,876 | 215,182 | 110.8 | 24 |
| ◇24.3* | 3,756,059 | 160,260 | 178,180 | 254,478 | 135.6 | 26 |
| ◇25.3 | 3,550,116 | 265,089 | 273,445 | 219,807 | 120.9 | 28 |
| ◇26.3予 | 3,450,000 | 360,000 | 385,000 | 390,000 | 219.4 | 30 |
出典元:四季報オンライン
キャッシュフロー
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 220,329 | -42,809 | -313,585 |
| 2024 | 309,221 | -157,239 | -181,488 |
| 2025 | 303,882 | -89,176 | -240,454 |
出典元:四季報オンライン
バリュエーション
| 年度 | 営業利益率 | ROE | ROA | PER(実績) | PBR(実績) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.0% | 13.5% | 6.5% | ― | ― |
| 2024 | 4.2% | 14.5% | 7.2% | ― | ― |
| 2025 | 7.4% | 12.6% | 6.2% |
高値平均 22.8倍 安値平均 15.7倍 |
3.74倍 |
出典元:四季報オンライン
投資判断
東芝の直近の売上規模は 毎年およそ3兆5千億〜3兆7千億円 と非常に大きく、日本を代表する総合電機メーカーとしての存在感は依然として強い。売上のボリューム自体は安定していて、急落したり極端に増減したりという乱高下は見られない。事業ポートフォリオが広く、インフラ、エネルギー、半導体製造装置、デジタル系サービスなどがバランスよく組まれているため、景気変動に対してそこそこ強い体質になっている。
営業利益を見ると、2023年は 3,356億円で営業利益率9.0% と十分な水準だったが、2024年は一度落ち込み、営業利益率も 4.2% まで低下。これは構造改革費用や一部不採算事業の影響が大きく、東芝全体の課題が表面化したタイミングといえる。しかし、2025年には営業利益が 2,650億円・営業利益率7.4% と回復基調に入り、2026年予想ではさらに 3,600億円・営業利益率10%超えに近い水準 を目指しており、再建が軌道に乗りつつある印象を受ける。
経常利益・純利益の動きも同じで、2024年のみ“落ち込み→持ち直し”の流れが見られる。2023年・2025年は純利益が2,000億円を超える水準に戻っており、2026年予想では 3,900億円の純利益 と非常に強気の数値が並んでいる。東芝としての力は依然として高く、収益構造の改善が確実に進んでいることが読み取れる。
ROE・ROAを見ても、
- ROE:12〜14%前後
- ROA:6〜7%前後
と、総合電機メーカーの中ではかなり高い水準。ROEがこのラインに安定して乗っている企業は、日本の大型株の中では優秀な部類に入る。自己資本をしっかり利益に変換していて、効率の良い経営ができていると判断できる。
また2025年の実績PERは高値基準で 22.8倍、安値基準で 15.7倍 とやや高めだが、大型再建銘柄としては「将来の収益改善が織り込まれている株価」だと理解すると違和感はない。完全な割安株ではないものの、上場廃止リスクなどが風化し、企業価値が正常化していく過程で市場が期待を上乗せしているとも読める。PBRは 3.74倍 と高く、これも「再編による価値見直し」「次世代事業への期待」を株価が反映している形だ。
総合すると、東芝は「売上規模の大きい安定企業」でありながら、過去数年のゴタゴタを乗り越え、収益性が確実に戻りつつある転換期の銘柄。短期的に割安感は薄いが、中長期で企業価値が正常化・拡大していくフェーズに入っている可能性は高く、安定して大崩れしづらい大型株として一定の魅力がある。
ただし、事業の多角化ゆえに“決定的な伸びしろの源泉がどこにあるか”はやや見えにくい面もあるため、株価上昇のスピードは急激ではなく“ジワジワ型”になる可能性が高いという印象だ。
配当目的とかどうなの?
富士通の配当について考えると、正直なところ「配当目的の投資先」としてはかなり物足りない部類になります。まず予想配当利回り(2026・2027年度)を見ると、26.3期が0.71%、27.3期が0.76%と、日本株の中でもかなり低い利回り水準に位置します。一般的に配当狙いの投資家が好む水準は2〜3%以上が目安とされるため、富士通の場合はその基準に遠く届かない状態です。
富士通はもともと高配当銘柄ではなく、どちらかと言えば事業成長や収益改善の期待を織り込み、株価上昇益(キャピタルゲイン)で狙うタイプの企業です。実際、直近の業績を見ても売上は3兆円規模で安定しており、営業利益・経常利益・純利益も毎年しっかり出しているため、企業体力は強い部類に入ります。
ただし、利益が増えても株主還元として大きく配当へ回すタイプではなく、内部留保や事業投資を優先する経営方針が明確です。そのため利益は出ているのに利回りが低い、という構造になっています。
また、PBRが3倍台、PERも高値平均で20倍超と、もともと株価が高めに評価されやすい銘柄なので、配当利回りが数字上どうしても伸びにくいという事情もあります。企業価値が高く評価されている分、利回りは自然と低くなる、といったイメージです。
結論として、富士通を配当目的で買うメリットはほぼ無いと言ってよく、インカムゲイン狙いの投資家には向かない銘柄です。配当金を年々積み上げていきたい人には物足りず、むしろ株主還元より成長投資を重視する企業なので、配当狙いで買うとミスマッチになりやすいでしょう。
配当ではなく、AI・IT投資需要の拡大やDX領域の拡張など、長期成長による値上がり益を期待する投資家向きの株だと考えるのが適切です。
今後の値動き予想!!(5年間)
現在の株価4173円を起点にして富士通の今後5年間の値動きを考えると、まず業績面では売上が3兆円規模で推移しつつも成長率は高くなく、利益率も年によって上下するため、株価の動きは「強い上昇トレンドが続く銘柄」ではなく、企業としての成長テンポに沿ってじわじわと評価が動くタイプになると考えられる。
良い場合は、グローバルのIT需要が強く、富士通が提供するサービス・システム関連の利益率が改善し、ROEや営業利益率が今より継続して改善したケースを想定する。特に2025年度以降に利益率が上向く流れが定着すれば、投資家評価が上がってPBRが拡大し、PERも高めで維持されるため、株価は5年でおおむね6000~7500円程度まで上昇する可能性がある。仮にAI・DX投資が国内外で拡大し、富士通がその恩恵をしっかり受けられれば、8000円前後も視野に入る。ただしこれは利益率・収益性の改善が継続することが前提で、何らかの停滞があれば上振れは難しい。
中間のケースでは、現状の富士通の収益性をほぼ維持しつつ、大きな成長も大きな悪化もない状態を想定する。この場合、株価は緩やかな上昇にとどまり、5年後は5000~5500円程度のレンジに収まると見て良い。売上が現状維持で推移し、営業利益率が5~8%の範囲を行き来するくらいなら、市場の評価も大きく変化しないため、株価水準も現在の4173円から少し上がる程度にとどまるだろう。つまり、短期的に大きく伸びるイメージではなく、じわじわ積み上がるような動きになる。
悪い場合のシナリオでは、国内外のIT投資が鈍化したり、コスト増加により営業利益率が圧迫されるケースが考えられる。特に富士通は固定費の割合が高いビジネス構造なので、利益率の低下は株価にストレートに効いてくる。ROEが10%を割る状態が続くようであれば、評価が下がってPBRが3倍を割り込み、PERも現在より低水準で放置される可能性が高い。この場合は株価が3000~3500円付近まで下落する可能性があり、外部環境が悪化した局面では2500円台まで落ちることも起こり得る。業績のブレが大きくなると市場からの評価は厳しくなり、株価は戻りが鈍くなる。
総合すると、富士通は配当利回りが高いわけではなく、成長企業としても爆発的な伸びがあるタイプではないため、株価の動きは「利益率改善に成功するかどうか」がすべての分岐点になる。上手くいけば6000円台~7000円台は狙えるが、成長が鈍れば5000円前後で停滞し、業績が悪化すれば3000円割れのリスクも残る。5年スパンで見れば、強気・中立・弱気がきれいに分岐する銘柄という印象で、今の株価水準はやや割高寄りではあるものの、業績の方向性次第でどちらにも振れやすい位置にあると言える。
この記事の最終更新日:2025年11月15日
※本記事は最新の株価データに基づいて作成しています。

コメントを残す